

最上川の川船は「※ひらた船」と呼ばれ、元禄から享保初年ごろには、内陸部では大石田船がほとんどで、「川船差配役(かわぶねさはいやく)」などの船役も、大石田が独占していました。それに対し上郷の商人たちは、新河岸設置と上郷川船差配役取立運動を起こし、今から280年前の享保8年(1723年)にそれが幕府に認められました。幕府は大石田河岸を無視する政策を実施し、大石田は商人荷物の中継権や川船所有の権利も一時失いました。
この時期は、ちょうど8代将軍徳川吉宗が享保の改革を断行していた時期に当たり、いわば享保の改革の一環として大石田が持つ舟運の既得権が取り上げられたこととなります。そのため、にぎやかであった大石田が火の消えたような淋しさになり、年貢米運搬業務だけでは利益が出ないために、次々と減船・廃業してゆき、町全体が困窮してゆきました。
それに対し、当時の町民たちは、粘り強く元の大石田のにぎわいを確保すべく幕府に働きかけ、18世紀の半ばに川船差配役の入札制となる中で、大石田河岸は一部復活しました。
大石田船は元禄末年には292艘ありましたが、宝暦11年(1761年)には120艘にまで減少、その後も減船し続けたため、幕府は最上川舟運を円滑に行う必要から政策を変更しました。具体的には、寛政の改革中の寛政4年(1792年)に大石田に新たに川船役所を設置し、総船持による川船会所を付設して、川船統制と差配を行うこととなりました。
大石田は、河岸として復活したばかりでなく、川船荷物を保管する荷問屋(にどんや)の新たな発展がありました。文化11年(1814年)には18人で荷問屋仲間を結成、天保7年(1836年)には、32人の荷問屋株仲間が結成され天保の改革でも解散されることはありませんでした。
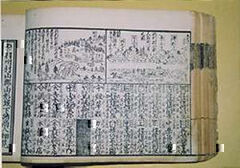
こうして見ると、享保の改革で幕府は大石田河岸を無視し、寛政の改革で大石田河岸を完全復活させ、天保の改革の直前には株仲間を新設させるという町の新たな発展を確認できたこととなり、いわば大石田河岸の歴史と日本の歴史とが連動していることがわかります。
※ひらたは舟編に帯
組織名(略称):総務課 総務グループ
住所:〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話番号:0237-35-2111
FAX番号:0237-35-2118
リンク(1):mailto:somu@town.oishida.yamagata.jp