おおいしだものがたり 第九十二話 「最上川舟運の話」 その6.大石田河岸の始まり
更新日:2016年3月25日
1.山形初代城主、斯波兼頼(しばかねより)が大石田に河岸を開く?
『大石田町誌』資料編(二藤部喜一郎家文書)によると次の記述があります。
「延文元年(1356年)、出羽国の按察使(あぜち・地方長官)として斯波兼頼が奥州大崎から最上(山形)へ入部してきました。山形に城を築き、居城しておりましたが、収納米を川下げするために、大石田と船町(山形)に河岸を造りました。そして、ひらた船を使ってはじめて酒田湊まで川下げしました。」
斯波兼頼は大石田と船町に同じ延文元年に河岸を造ったことになります。今もって船町に「修理太夫(しゅりだゆう)(斯波兼頼)殿蔵屋敷跡」といわれる所が残っていると言います。
延文元年とは、室町時代の足利尊氏将軍の時に当たります。しかし、本格的な河岸の造営は慶長年間、最上義光の時代になってからというのが通説となっています。
2.大石田河岸の区域
この当時、上記資料によると大石田河岸は中心部の本河岸の他に4か所の船場をもっていました。深堀・芦沢・名木沢・毒沢です。これらは、「大石田河岸の内」とされ、船着場とか川辺と呼ばれていました。さらに時代が下がると、小菅・大浦等も「大石田河岸の内」に加わるようになります。
これらの船着場は、主に年貢米の船積み場としての利用が許されていました。いわば農民のために利便を図った船場に過ぎませんでした。商用荷物等は、大石田の本河岸において揚げ下げされりことが決まりになっていました。
3.大石田に「ひらた船製造所」ができる
「大石田村は、最上(山形)城主の時代から、最上川通船のためのひらた船製造所を持ち、造船の仕事で渡世をしている人々がいました。その当時はまだ、外の村にはひらた船を造る所はありませんでした」(『大石田町史 史料集二』「最上川船差配転変之姿」)。
上記の史料が示す通り、最上川の通船及び河岸はその土地の領主(支配者)によって開かれ、用船は安全で大型のひらた船を使用することがほぼ定まってきます。大石田がそのひらた船の独占的な製造基地となっていることが分かります。
大石田の船大工の技術は高く評価されていたものとみえて、米沢藩では五百川(いもがわ)峡谷の舟運を成功させるために、元禄元年(1688年)に白鷹荒砥の正部村に大石田の船大工高橋正兵衛を移住させ、技術指導に当たらせたと言います。(「最上川五百川峡谷の舟道」米沢中央高校 佐藤五郎氏論稿)。
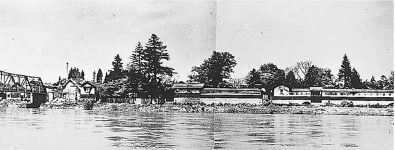
当時、河岸とされたところ
執筆者 小山 義雄氏
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

